2021年07月29日
十府ヶ浦的ルアー考
十府ヶ浦でヒラメに使うルアーについて、私の変遷です。

まず十府ヶ浦についてですが、周辺ではそれなりの規模のサーフと言ったらここしかない、それが十府ヶ浦です。
場所バレ以前に岩場だらけの海岸の希少な砂場なのでハナから地理的に浮いてます。
特別ヒラメが釣れるかと言えばそうでもないので遠征かけるなら青森太平洋側とか仙台仙南行った方が良いと思います…。
水深は10m超のドン深でも無ければ遠投しても2mとかの遠浅でもない深そうで深くない少し深いサーフです。
その箇所にもよりますが5〜7mくらいですかね?
波足が長いことも多く遊泳禁止です。
また小豆砂と呼ばれる砂質で粒が大きめです。

以下は私の十府ヶ浦ヒラメルアー変遷です。
【入門時】
お金も知識もないこの頃…。
パワーシャッド4inにがまかつのジグヘッドを付けてました。
レンジスイマータイプリバーシブルの18gでした。
静ヘッド14gの時もありました。
当時の初心者にありがちな「ソフトルアーへの信頼感≒ハードルアーへの不信感」が払拭できず基本的にワーム使ってましたねえ…。

【色々試した時期】
ルアーくらいならいくらか買い足せるようになって幅を広げてみるようになりました。
メーカーがフラット用に色んなルアーをラインナップするようになったのもこの時期でした。

そして、気づき始める「小豆砂」の恐ろしさ。
私はストップ&ゴーを中心に組み立てています。
理由はそれなりに水深があるので底を切りすぎていないか確認したいからです。
1回のリトリーブで3、4回着底させることが多いです。
それで5回くらいのリトリーブでフックが爪に掛からなくなります。
もっと粒の小さいサーフでやったこともありますが同じ釣り方しても明らかに磨耗が早いです。
時化気味の時だとさらに早まります。
マズメ時に研ぐのも時間が勿体ないのでマルトフックをまとめ買いして頻繁に交換するようになります。
と、同時に2フック以上搭載されているルアーの運用について考えるようになります。
「フック交換が可能」という美点があるビーチウォーカーハウルや、「高シンクレートとボリューム感に加えてただ巻きでも高アピール」が出来る飛びすぎダニエルも使ったりはしたんですが…
朝マズメにフックポイント6箇所の点検・交換が煩わしくなってきました。
ルアーのフォール姿勢にもよりますがテールフックが早く摩耗します。
水中でのルアーのレンジをイメージできるか、比較的上のレンジを探ることにアレルギーが無いアングラーであればマルチフックのルアーも問題ないと思います。
砂質ともうひとつ、波足の長さも特徴です。

水深のあるサーフなので飛距離は必要なさそうですし、ヒットするのもほとんどが手前のブレイクです。
ただ、波足が長いんです。
基本的に波打ち際から下がった状態でのキャストを強いられます。
その為水深があるのに飛距離も必要となる…。
波打ち際での抵抗も大きくなるので引き抵抗も少ない方がストレスフリーです。
結局今はオーソドックスなメタルジグにシングルのアシストというなんの個性も無いフォーマットに落ち着いています。


凪で波足が非常に短い日は朝イチヘビーシンキングミノー投げたり、粘りたい箇所ではシンペン使ったりすることもありますがほとんどジグで通してます。
逆にワームの投入機会が激減しました。
遅い釣りができるという利点があるので活性が悪いと判断できたら積極的に投入した方が良いのでしょうね。
ただ、その境地にはまだ至っておりません…。

まず十府ヶ浦についてですが、周辺ではそれなりの規模のサーフと言ったらここしかない、それが十府ヶ浦です。
場所バレ以前に岩場だらけの海岸の希少な砂場なのでハナから地理的に浮いてます。
特別ヒラメが釣れるかと言えばそうでもないので遠征かけるなら青森太平洋側とか仙台仙南行った方が良いと思います…。
水深は10m超のドン深でも無ければ遠投しても2mとかの遠浅でもない深そうで深くない少し深いサーフです。
その箇所にもよりますが5〜7mくらいですかね?
波足が長いことも多く遊泳禁止です。
また小豆砂と呼ばれる砂質で粒が大きめです。

以下は私の十府ヶ浦ヒラメルアー変遷です。
【入門時】
お金も知識もないこの頃…。
パワーシャッド4inにがまかつのジグヘッドを付けてました。
レンジスイマータイプリバーシブルの18gでした。
静ヘッド14gの時もありました。
当時の初心者にありがちな「ソフトルアーへの信頼感≒ハードルアーへの不信感」が払拭できず基本的にワーム使ってましたねえ…。

【色々試した時期】
ルアーくらいならいくらか買い足せるようになって幅を広げてみるようになりました。
メーカーがフラット用に色んなルアーをラインナップするようになったのもこの時期でした。

そして、気づき始める「小豆砂」の恐ろしさ。
私はストップ&ゴーを中心に組み立てています。
理由はそれなりに水深があるので底を切りすぎていないか確認したいからです。
1回のリトリーブで3、4回着底させることが多いです。
それで5回くらいのリトリーブでフックが爪に掛からなくなります。
もっと粒の小さいサーフでやったこともありますが同じ釣り方しても明らかに磨耗が早いです。
時化気味の時だとさらに早まります。
マズメ時に研ぐのも時間が勿体ないのでマルトフックをまとめ買いして頻繁に交換するようになります。
と、同時に2フック以上搭載されているルアーの運用について考えるようになります。
「フック交換が可能」という美点があるビーチウォーカーハウルや、「高シンクレートとボリューム感に加えてただ巻きでも高アピール」が出来る飛びすぎダニエルも使ったりはしたんですが…
朝マズメにフックポイント6箇所の点検・交換が煩わしくなってきました。
ルアーのフォール姿勢にもよりますがテールフックが早く摩耗します。
水中でのルアーのレンジをイメージできるか、比較的上のレンジを探ることにアレルギーが無いアングラーであればマルチフックのルアーも問題ないと思います。
砂質ともうひとつ、波足の長さも特徴です。

水深のあるサーフなので飛距離は必要なさそうですし、ヒットするのもほとんどが手前のブレイクです。
ただ、波足が長いんです。
基本的に波打ち際から下がった状態でのキャストを強いられます。
その為水深があるのに飛距離も必要となる…。
波打ち際での抵抗も大きくなるので引き抵抗も少ない方がストレスフリーです。
結局今はオーソドックスなメタルジグにシングルのアシストというなんの個性も無いフォーマットに落ち着いています。


凪で波足が非常に短い日は朝イチヘビーシンキングミノー投げたり、粘りたい箇所ではシンペン使ったりすることもありますがほとんどジグで通してます。
逆にワームの投入機会が激減しました。
遅い釣りができるという利点があるので活性が悪いと判断できたら積極的に投入した方が良いのでしょうね。
ただ、その境地にはまだ至っておりません…。
Posted by りきお at 22:39│Comments(0)
│タックルあれこれ











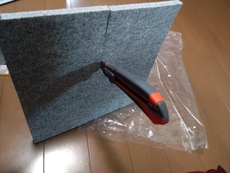









![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/192b0811.262b8d71.192b0812.810725b6/?me_id=1238682&item_id=10014602&m=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Ffishingsanin%2Fcabinet%2F00772645%2Fimgrc0081319439.jpg%3F_ex%3D80x80&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Ffishingsanin%2Fcabinet%2F00772645%2Fimgrc0081319439.jpg%3F_ex%3D64x64&s=64x64&t=picttext)




